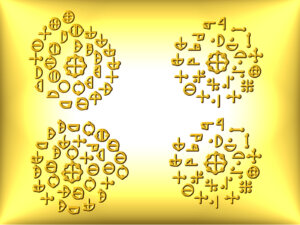こんにちは、風と土の自然学校 梅崎靖志です。
4月になりました!いかがお過ごしですか。

さて、僕の住む八ヶ岳は、
あたたかくなってきて、とても気持ちの良い季節です。
草たちも、ようやく顔を出し始めました。
畑での収穫が、本格化するのは
まだこれからの今の時期、
野にはたくさんの食べられる
おいしい野草が生えてきます。
身近で見つかる食べられる野草
春の食べられる野草といえば、
タラの芽、コゴミ、ワラビ、
カンゾウなどなど、
こうしたイメージかもしれません。
ところが、
身近に生える野草にも、
おいしく食べられるものが
たくさんあるんです。
身近に生える「野草」といえば、
聞こえはいいけど、
つまりは、その辺に生える
いわゆる「雑草」です(笑)
こうした草たちの中で、
おいしく食べられるものには、
スギナ、ヨモギ、ハルジオン、
ヒメジョオン、ヒルガオ、オオバコ、
ハコベなどなど、
わが家のまわりだけでも
20種類以上、すぐに見つかります。
もちろん、みなさんのご自宅のまわりにも
たくさんの食べられる草たちがあるんですよ。
薬草としても活用できる
雑草たち
こうした野草(雑草)は、
食べられるだけでなく、
薬草として使えるものもいろいろあります。
たとえば、ヘビイチゴの実。

赤い実を集めて、ホワイトリカーに
漬けるだけでチンキを作ることができます。
これが、虫刺されのときのかゆみ止めとして
絶大な威力を発揮します。
わが家の常備薬です。
民間薬として使われてきたものは、
ほかにもいろいろあります。
ヘビイチゴは、見分けるのが
簡単な部類ですが、
なかには、
「本当にこれであってる?」
と迷ってしまうこともあります。
写真やイラストと比べるだけでは、
確信が持てず、不安でなかなか手が出せない
という方も多いんです。
実際、毒草を間違えて食べて中毒を起こした、
というニュースもよく見聞きしますね。
身近な野草を安心して
使えるようになるには?
植物には興味がある。
でも、自信を持って見分けることがなかなかできない、
という方には、共通点があります。
それは、何かといえば、
図鑑の写真やイラストだけで、
種類を見分けようとしている、
ということなんです。
写真やイラストと比べて調べる、
いわゆる「絵合わせ」では、
やっぱり限界があります。
ではどうすればいいのか、といえば、
ポイントは、たったひとつ。
それは、解説文を読む、ということ。
これだけです。
ところが、解説文は専門用語が
並んでいて、読んでいても何のことか
さっぱりワカラナイ・・・

日本語で書かれてはいるけど、
そもそも、漢字の読み方がワカラナイ、
なんていうことも、しばしばです。
葉柄、鋸歯、対生、葉鞘、葉舌、托葉、、、
それぞれ、
ようへい、きょし、たいせい、ようしょう、ようぜつ、たくよう
と読みます。
葉柄とは、枝から伸びた葉っぱの柄のこと。
鋸歯とは、葉っぱのギザギザのこと。
こんな感じで、一見、難しそうに見えても、
実物を見ながら覚えれば、すぐに覚えられます。
また、重要な植物用語というのは
それほど数が多くないので、
基本がわかってしまえば、初めての人でも
図鑑の解説文がどんどん読めます。
そして、解説文には、
見分けるポイントが書かれていますから、
意味がわかりさえすれば、
だれでも、植物の識別が正確にできるように
なるんです。

図鑑の使い方の基本がわかれば、
自分で植物検索できるようになります。
でも、一番はじめのとっかかりの部分は、
一人で取り組むと、とても骨が折れるので
挫折してしまう人がほとんどです。
ところが、ポイントを教わりながら、
仲間と一緒に取り組むと、
最初のハードルを楽々と越えることができます。
ここさえ越えれば、後はひとりでも、
楽しめるようになっていきます。

あっと驚く、おいしい野草料理!
野草料理の定番といえば、
天ぷらやおひたし、そして酢味噌和え。
ところが、野草料理には、
様々なバリエーションがあります。

私たちが毎年開催している野草講座では、
インドの生命科学 アーユルヴェーダの先生で、
料理研究家のタミちゃんこと、
ミヤモトタミコさんと
森林インストラクターでもある
この道30年のうめちゃんこと、梅崎が
講師を務めています。
タミちゃんの手にかかると、
いわゆる雑草たちが、たちまち素敵な
おいしい料理に変身します。

ドクダミの葉を生春巻きに
使ったときには、
正直「えーっ!?」と思いました。

ところが、食べてみたら、
あれ、これはパクチーのような
香草じゃありませんか〜

もう、本当に、
目からうろこが落ちるとは
このことです。
毎年、季節を微妙に変えて開催しているので、
野草の顔ぶれが変わります。
そのため、様々なおいしい料理が繰り広げられます。
野草図鑑のひき方がわかり、
身近な野草のおいしい料理を楽しめる、
2日間の講座を、
2025年5月3〜4日(土日)に
開催します。
八ヶ岳の「風と土の自然学校」が会場です!
アーユルヴェーダの野草料理 & 草本図鑑の引き方講座
図鑑の引き方と、おいしい食べ方を実践から学び
安全安心に野草を楽しめるようになる!
開催日
〜4日(日)15:30
↓↓↓
ちなみに、会場となる「風と土の自然学校」の
最寄り駅は、JR中央線の小淵沢駅、
インターなら、中央自動車道 小淵沢インター
どちらも、自然学校まで車で10分ほどです。
ご興味とタイミングが合う方と、
ご一緒できるのを楽しみにしています!

これまで、東北地方や中国地方などの
遠方からもお越しいただいています。
「私のところから、どのくらいかかるのかな?」
と思ったら、ぜひ調べてみてくださいね。
昼過ぎにスタートするので、
仙台や大阪からでも十分に間に合います。
では、よいゴールデンウィークをお過ごしください!