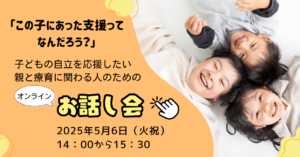今回は、初秋の時期におすすめの種まき法「混播(こんぱ))」に
ついてご紹介します。
古くなった種子や余った種子を有効活用できる、
実用的な方法です。
風と土の自然学校の畑でも、毎年、
お盆の頃から9月の上旬にかけて、
混播をしています。
混播が普通の種まきと一番違うのは、
草むらに直接タネを蒔くところ。
年間講座で紹介すると、
「え、それでいいの?」とみんなが驚く
種まきの具体的なやり方をご紹介しますね。
コンパ(混播)とは?
コンパ(または「コンパン」)は、
様々な野菜のタネを混ぜてまく混植栽培のひとつです。
「混ぜ蒔き」とも呼ばれ、以下のような効果が期待できます。
環境にあった作物が育つ:その場所の環境に最も適した作物が育つ
多様性の向上:複数の作物を一緒に育てることで、相互に助け合って成長
リスク分散:一つの作物が失敗しても、他の作物でカバーできる
古い種子の有効活用:発芽率の下がった古い種も、ムダなく利用できる
コンパに適した時期と作物
最適な時期
8月下旬から9月上旬がベストタイミング
・ 夏草の勢いが弱まり、冬草に入れ替わる時期
・冬がやってくる前に、作物が成長できる期間が確保できる
なお、春先は、夏草の勢いが強くなっていく時期なので、
同じように播いても草に埋もれてしまいます。
適した作物
アブラナ科の葉物や根菜類がオススメです。
このほか、シュンギク(キク科)なども大丈夫。
具体的には、
大根、カブ、小松菜、チンゲンサイ、シュンギクなど
手元にあるちょっと古くなったタネを混ぜて播きます。
コンパのやり方
1. 種の準備と散布
1. ちょっと古くなった様々な野菜のタネを混ぜる

2. 草は生えた状態の草むらに、適度な量をバラマキする
3.タネが 均一になるように、少しずつ何度も往復しながらまく

2. 草刈りと敷き草作業
1. 種を播いたら、地際から草を刈る
2. 刈った草は、その場に敷く
3. 草を軽く揺すって、種が確実に地面に着地するようにする

3. 種まきのタイミング
・朝露や雨上がりなど、草が濡れている時間は避ける
→濡れた草に種子がくっついて、着地しにくいため
4. 敷き草の厚さを均一に整える
・敷いた草は、薄いところと厚いところがないよう、均一に調整する
→ あまり敷き草が厚すぎると芽が出にくくなので、
地面が隠れる程度に、適度な厚さにします
コンパの特徴・成功のポイント
土をかける必要なし!
一般的な種まきと異なり、コンパでは種に土をかける必要がありません。
刈った草を地表に敷いた保湿効果で、土をかけなくても発芽します。
タイミングが重要
・草の勢いが強くなる春先は、作物が草に埋もれてうまくいきません
・種まきが遅すぎると、十分に成長する前に冬が来てしまいます
・8月半ば〜9月上旬の種まき、オススメのタイミング(地域差があります)
発芽後の草刈りがポイント!
発芽後には、草刈りの管理が必要です。
晩夏〜初秋と行っても、まだまだ草たちも大きくなります。
様子を見ながら、野菜の芽が草に埋もれてしまわないように
2〜3回、草刈りをしましょう。
また、野菜の芽が混み合ってきたら、適度に間引きします。

収穫時期
10月から11月にかけて、様々な葉物野菜や大根などが収穫できます。
間引きを兼ねて、順次収穫を楽しむのもオススメです。
コンパをしてみよう
畑の一角に、草がたくさん生えているところがあれば、
コンパを試してみませんか。
古いタネを活用しよう!
春先に用意した、様々な野菜のタネも、
畑の広さの都合で、播ききれなかった
とか、
タネをしまってある箱を確認したら
数年前の余ったタネが出てきた
ということはありませんか?
タネの寿命は、野菜の種類によって異なります。
キュウリのように3〜4年経っても
ちゃんと芽が出るものもあれば、
ネギやニンジンのように、
2年も経つと、ガクンと発芽率が落ちるものもあります。
古いタネは、せっかく蒔いても、芽があまり出ないかも、
でも、捨ててしまうのは忍びない、、、
というときこそ、コンパの出番です!
晩夏〜初秋の時期に、ぜひ試してみてください。
自然農の基本やタネについて知りたい方へ
風と土の自然学校では、
耕さず、草も虫も敵としない「自然農」と
自然と調和した循環する暮らしを実践する
「パーマカルチャー」の考え方をベースにした
手づくり循環生活をテーマにした無料メルマガ
「風と土の便り」を配信しています。
また、9月には、
オンラインのお話し会を開催します。
詳細ページは、
こちらをクリックするとご覧いただけます。
できることから少しずつ。
手づくり循環生活のコツは、
楽しみながら小さく始めることです。
ぜひ、コンパをお試し下さいね!